|
「消化酵素の多様性と進化」
景山 節
霊長類の胃の消化酵素ペプシンは胃粘膜で前駆体のペプシノゲンとして合成され、胃液として分泌される。ペプシンはタンパク質分解酵素なので、胃で消化するのはもっぱら食物中のタンパク質である。いろいろな哺乳類の胃粘膜で合成されるペプシノゲン量は食性と明確な相関があり、植物食(単胃)>雑食>肉食>植物食(反芻胃)の順でペプシノゲン含量は高く、最も高い含量を示すのは霊長類である。この結果は植物食の動物では胃で多量のペプシノゲンを合成していることを示す。植物には細胞壁成分のセルロースや代謝物のフェノール性物質などが多量に含まれており、これらの物質はペプシン活性を阻害することから、効率的な消化のためには多量のペプシンが必要となったと推測される。
ペプシンは胃のある動物、すなわち脊椎動物に発現している。祖先はカテプシンEと呼ばれるプロテアーゼである。最も古い祖先酵素は酵母にまで遡ることができ、液泡のプロテアーゼに由来している。もともと1成分だったと推測されるが、遺伝子重複で数を増やしてきて、現在では5成分になっている。これらは、A,B,C,F,Yと区別されます。各動物がこれらすべてをもっているわけではなく、欠損やあるいは逆に重複が頻繁に見られそれぞれの発現は動物間でかなり異なっている。
霊長類の祖先でもペプシンの主要成分であるA成分は1遺伝子で、この状態は新世界ザルまで続いている。3000万年くらい前にニホンザルなど旧世界ザルが分岐し、それ以降、急にペプシン遺伝子増幅がおこっている。この傾向は今でも進行中のようで、オランウータンでは遺伝子重複で数が非常に増えてきたことがわかっている。
ヒト化に向かう過程で数を増やして来たことは大脳の発達と無関係ではなく、体が大型になりさらに急速に大きくなった大脳の機能を維持するには、神経伝達物質や機能ペプチドの要素としてのアミノ酸の供給が必須となり、消化効率を上げることが必要だったのではないか。
動物が環境に適応するために新たな食性を採用したときは、ペプシンはそれに対応して機能を変えてきた。ヒトやサルに多いA成分と、肉食類に見られるB成分を比べてみると、全体のアミノ酸配列の相同性は50%以下で半分くらいが違っているが、機能に関係した重要な変化は2つのアミノ酸がもたらしている。機能の違いと、それに関与するアミノ酸変異はいずれも2-3個の決定的な変化が起こることが必要である。
|
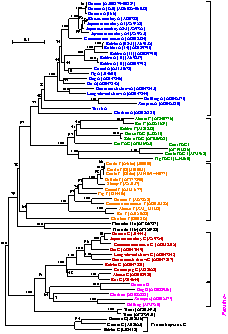
図 ペプシン遺伝子の進化
|
戻る
「ヒトの進化とエネルギー問題-脂肪と脳と家族」
濱田 穣
ヒト(人間、人類)の最も著しい特徴は、なんといっても大きな脳である。容量で1300-1400ccもある。ヒトに近縁で、知能も高いチンパンジーでは400ccほどである。高度に発達した脳の効能は計り知れない。大型の脳が、そんなに効果があるのなら、なぜ、人類だけで発達し、他の動物たちでは発達しなかったのだろうか?
脳サイズは生物のもつ様々な特徴の一つである。特徴が進化する基本は、ゲノム(遺伝子)の変化である。しかも、それによって変化した特徴がその生物の生き方に合致し、それを発展させるときに、その変化が受け入れられ(適応)、種は進化する。進化は基本的には遺伝的変化という必要条件と、適応という十分条件の両方を必要とする。
大きな脳が進化するための十分条件とは何なのか?脳はぜいたくな器官で、糖(グルコース)しかうけつけず、その消費スピードが速く、供給が滞ると、すぐさま障害をひきおこす。したがって、十分に食物獲得ができなければ、大きな脳を養うことができない。すべての生物種はエネルギー(食物)問題に「頭を悩まし」、多様なエネルギー獲得の方法を進化させることで、多様化した。当然、エネルギーの使い道にも気を使う。生まれ、育ち、オトナになって繁殖し、死んでいくという生涯の過程において、エネルギーの使い方は、その生物種の特徴として進化過程で最適化されていると考えられる。
人類はエネルギーをどう獲得し、それを使っているのだろうか?ヒトの特徴は、家族のなかで子を育てること、すなわち夫婦(父母)が子育てする(エネルギーを子へ投資する)。さらに祖父母の貢献もある。ヒト以外の霊長類では、大多数の種で、子を育てるのは母親だけである。アカンボウを母乳で育てるのは、ヒトも同じだが、離乳すると食物を与えない。ところがヒトでは離乳後のコドモにも食物を与える。トラやオオカミといった肉食哺乳類もこのような育児法をとっている。その理由は、コドモが餌を捕れないからである。ヒト以外の霊長類のコドモは、オトナと同様の食物を採ることができるが、ヒトの食物はコドモには得難い食物である。狩猟による獲物(肉)、道具を使わないととれない食物(例、イモのような地下にできる食物)、効率よく採取する必要がある穀類などである。狩猟・採集した食物を家族の居住地区(ベースキャンプ)へ運搬し、そこに留まっているコドモに与える。ヒトの特徴である直立2足歩行は、この生活方法の進化の十分条件のひとつであり、ひいては脳の拡大の基礎的条件となった。
脳とならんで、隠れたヒトのもうひとつの特徴は、豊富に蓄積された体脂肪であり、それはエネルギー問題解決の象徴である。現代のオトナの男性で脂肪率が15-20%、女性で20-25%が健康的な標準値であるとされる。ヒト以外の霊長類に、こんなに高い脂肪率を持つ種はない。たいがいが5-10%ほどである。ヒトではオトナとならんでアカンボウでも脂肪率が高い。大きな脳の維持と発達には、大量の、そして途切れないエネルギー供給が必要であり、体脂肪がそれを保障するのである。
ヒトの進化における、家族・分業・育児・脳・学習について考えてみたい。
戻る
「屋久島のニホンザルの人口変動と社会変動」
半谷 吾郎
屋久島では、野生のニホンザルの調査が30年以上にわたって継続して行われています。1974年以来、人里から離れた西部海岸部の複数の群れの調査が行われてきました。30年間の調査で分かったことは、ニホンザルの群れは、決して安定ではなく、時間とともに大きく変動する存在だということです。1980年代前半までは、個体数の増加と対応して、群れの分裂が頻発しました。ところが、1980年代後半から、個体数を減少させる群れが増え、中には非常に小さくなって他の群れと融合し、消滅してしまう群れもありました。1999年には大量死が発生し、二つの群れが突然消滅するとともに、その周りの群れも大きく数を減らしました。これらの社会変動には、果実生産の年変動が大きくかかわっています。豊作の年には出産率は群れによって変わらなかったものの、不作の年には小さい群れで子供が生まれず、群れの大きさの差がますます拡大して行ったのです。また、大量死の年は、過去に例を見ないほど不作の年でした。
一方、同じく野生のニホンザルの長期調査が行われている宮城県の金華山島では、個体数の変動は見られますが、小さな群れが不利になるようなことはありません。残念ながら、これらの長期調査地では、環境の年変動、個体数の変動、社会変動を同時に調査していたわけではなく、彼らの社会のダイナミックな変動が、環境変動とどのようにかかわっていたのか、推測の域を出ません。
わたしたちは、屋久島の標高1000m付近に新しい調査地を設定し、1998年から継続調査を始めました。ここは海岸部の長期調査地から7kmほどしか離れていませんが、ヤクスギ林に覆われ、海岸部とは大きく異なった環境です。植生や果実生産の年変動、個体数密度、複数の識別された群れの構成と分布を、ボランティアで全国から集まった数十人の学生とともに毎年調べています。屋久島海岸部とあわせて、野生霊長類個体群の動態の空間的変異を明らかにするという、稀有な試みが、屋久島で始まろうとしています。
|

抱き合う屋久島のニホンザルの兄と妹
|

大量死のときに発見された 白骨死体
|
戻る
「会話が心を育てる―ヒトのコミュニケーション力の発達」
松井 智子
われわれは当たり前のように他者から情報を受け取るが、それは実はコミュニケーションという人間に与えられた特権による恩恵に他ならない。対照的に、人間以外の大多数の動物にとっては、自らの観察が唯一の情報源なのである。ハチのダンスやベルベットモンキーの警戒音は動物のコミュニケーションの例としてよく知られているが、これらは人間のコミュニケーションとふたつの点で大きく異なっている。ひとつめは、情報の豊富さである。人間が知覚でき、伝達できる情報の豊富さに比べ、動物が伝達できる情報は非常に限られている。ほとんどが遺伝的に決定されているという見方もある。ふたつめは、言語の創造性である。人間は言語形式と意味の関係を柔軟に操ることができ、それらの新たな組み合わせを創出することによって、これまでになかったアイデアを伝達することができる。それに対して、動物は、自ら新たな音声やジェスチャーの組み合わせを作ることはない。
進化心理学の仮説によれば、人間の言語能力も、コミュニケーションに必要な社会的能力も、進化的適応であり、人間に普遍的に備わっている先天的な能力と捉えられる。近年ますます盛んになっている赤ちゃん研究の結果からも、その仮説を支持する結果が多く出されている。たとえば赤ちゃんが母親の声を好んで聞くことや、言葉とそれ以外の音を聞き分けること、そして自分の行動に反応を示してくれる相手を好むことなどは、コミュニケーションの基盤が生まれつき備わっていることを強く示唆している。
一方、言語コミュニケーションの初期発達については、まだ研究が十分とはいえない。子供は2歳前後から語彙を獲得し始め、3歳になれば大人と対等にコミュニケーションに参加できるようになるが、その時期の社会的能力はどのような特徴を持っているのか、先天的に持ち合わせている基盤的な力が、実際に言語を操りコミュニケーションの経験を積むことでどのように変化を遂げるのかについては、まだまだわからないことが多い。そこで、今回は、特に3歳児のコミュニケーション能力に焦点を当てて、これまでの知見を振り返るとともに、新しい調査の結果を紹介し、この時期の社会認知発達について考えてみたい。2歳から3歳にかけての家庭での日常会話が、その後の子供の心の発達に重要な意味を持つことが明らかになりつつある。言語獲得には、遅くとも8歳くらいまでに十分な量の母語に接していることが不可欠であるのと同様に、人間が生まれつき持っているコミュニケーション能力をさらに発展させるためにも、安定した社会との相互作用が不可欠だと考えるべきかもしれない。
戻る
|







