野生チンパンジーとは何か-文化と本能の接点を探って
ハフマン、マイケル(生態機構分野)
近年、動物の文化的行動(Culture又はBehavioral Tradition)研究が再び学界で注目を浴びている。特に「チンパンジー文化」についての研究が急ピッチで進んでいる(e.g.
Whiten et al. 1999, Whiten, 2005 NATURE)。ニホンザルのイモ洗い行動から出発した霊長類の文化的行動に関する研究は、何らかの社会的影響をうけて個体間を通して伝達するとされている。新しい行動が学習によって獲得されることもあるが、系統特有の行動が遺伝することもある(innate
behavior)。人間や学習能力の高いチンパンジーを含めて、この両方の獲得形態(学習、遺伝)によって個体の行動レパートリーが形成されてゆくと考える。
While the literature on putative culturally derived behavioral variation
between different populations of the same species or sub-species is growing, few
studies have attempted to look at the biological and ecological influences
behind culture. One important problem left unsolved, is how much of what an
animal in the wild does and 'knows' is learned and how much is based on innate
behavioral propensities of the species or genus acquired over the species'
evolutionary history. To be sure this is a difficult question to answer because
field workers are unable to manipulate the environment and it is extremely
difficult if not impossible to follow the emergence of a new behavioral
innovation and transmission throughout the group in detail. I am interested in
this process, and in 2001 began a behavioral and ecological investigation of an
introduced population of zoo raised chimpanzees into the wilds of Tanzania.
Rubondo Island National Park, Tanzania, is far outside of the natural range of
chimpanzees, but the vegetation is a mosaic of plant species used by chimpanzees
elsewhere as food. This was a serendipitous release of 17 juvenile chimpanzees
into a totally new environment, done without any human intervention or the
benefit of mature wild raised chimpanzees to show them how to survive in the
wild. Forty years have past, providing a perfect opportunity to see how
chimpanzee they really have become without the benefit of a locally relevant
cultural tradition to follow. The research is still in progress, but it is
already clear that they have learned by themselves how to survive. The
population has more than doubled in size showing that they have found nutritious
food and are able to reproduce. This in itself may not be so surprising. But
they also form social groups, hunt for meat, use tools for insect foraging and
make sleeping nests. While these behaviors are generally the same as those of
wild chimpanzees in other parts of Africa, they differ in some interesting
aspects that make them unique from chimpanzees observed in the wild elsewhere.
It is hypothesized that the last 2-3 generations of offspring born onto the
island depend more upon the acquired knowledge of their founding descendants,
and much less if at all on individual trial and error, that is these behaviors
are transmitted across generations via social learning processes, forming the
beginnings of a Rubondo chimpanzee culture. Ultimately, genetically based
behavioral propensities and trial and error are fall back mechanisms for
survival, but under more stable and predictable environmental conditions
adjustments to changing environmental conditions occur through social learning
and are imbedded with a group as culture. In short, like humans, chimpanzees and
indeed all other animals are neither pre-programmed robots nor sentient beings
free from our biological heritage and ecological surrounding.
危機に瀕している霊長類 ― 霊長類の保全と管理
室山泰之(ニホンザル野外観察施設)
現在地球上には200種以上の霊長類がいるといわれており、多くの霊長類種が絶滅の危機に脅かされている。2002年のIUCNレッドデータブックによれば、約半数にのぼる19種が絶滅危惧IA類(Critically
Endangered)に、46種が絶滅危惧IB類(Endangered)に、53種が絶滅危惧II類(Vulnerable)に分類されている。
なぜこのような事態になったのか、ということにはいまさら言及する必要はないかもしれない。地球温暖化や酸性雨をはじめとして、人間が地球という惑星の自然を劇的に変化させてきたことには、疑いの余地はないだろう。人口の増大、農業や工業などの産業活動、森林伐採、開発など、人間はその生息範囲をどんどん広げてきた。その結果、ほかの生物たちの生息地は荒廃し、さまざまな生態系が汚染され、数え切れないほどの動植物が過剰収獲によって絶滅した。また、新しい土地へと進出する過程で持ち込んださまざまな外来種は、それまでその地域で進化してきた在来種の絶滅を広範囲に引き起こした。生物の世界では、まさに破滅的な状況が起こっているといっても過言ではない。冒頭に述べたように、霊長類も例外ではなく、多くの種が絶滅の危機にさらされている。
この講義では、霊長類の現状とその存続を脅かしているさまざまな要因について概説するとともに、わたしたちに馴染みの深いニホンザル(Macaca
fuscata)の現在の状況について説明したい。
生きることは変わっていくこと
清水慶子・大石高生(器官調節分野)
生命は常に外界と相互作用し、自らも変化している。進化は最も長いタイムスパンでの生命のありかたの変化といえる。霊長類の一個体に限定して話を進めても、受精卵からスタートする発達、発育、成熟そして老化の過程で身体の構造も機能も変化していく。さらに、より短いタイムスパンでも生理機能はさまざまな種類の変化を示す。今回の講義では、生体内の代表的な調節機構である内分泌系と神経系がそのような変化にどのように関わっているかを二つのトピックスに絞って紹介する。
まず前半では、生殖機能の成長・発達・加齢を主に内分泌系の視点から解説する。ヒトを含む哺乳類では、性腺は一般に卵巣・精巣のいずれにも分化可能な生殖腺隆起と呼ばれる原基として発生する。すなわち、生殖腺隆起は性分化の過程を経て内外生殖器を形成し、オスかメスかどちらかの胎児に変わる。次いで、母胎から出て新生児へと変わり、乳児、幼児と成長し、思春期を経て性成熟をむかえ、オトナに変わる。オトナの時代はしばらく続き、老年へと変わり、最後は命を終える。このように個体が生きるということは変わっていくことに他ならない。一生のうちで発育速度が最も早いのは胎児期で、次いで乳児期である。思春期には急速な身体発育、成熟がみられるように、乳児期以降ではきわめて発育のスピードの早い時期として特徴づけられる。本講義ではホルモンや成長因子から見たニホンザルの個体や生殖機能の成長・発達・加齢について、これまでの我々の研究結果を中心に新しい知見を紹介する。
ひきつづき後半では、脳損傷からの機能回復について解説する。脳は動物が生きるために進化してきた情報処理装置である。脳は、あるいはその主要構成要素であるニューロンは絶えず自らを取り巻く環境と相互作用しながら変化している。霊長類の脳は長い時間をかけて発達し、その間も、そして成熟後も経験を反映させながら構造的にも機能的にも変化していく。脳のこのような性質「可塑性」は適応的な性質であり、基礎研究の側面からも、応用面への展開からも高い関心を持たれている。今回の講義では、特にわれわれが最近取り組んでいる「中枢神経損傷後の機能回復過程」について解説する。サルは指を独立に動かし、精密把握などの巧緻な運動をすることができる。その神経的な基盤になっているのが、主に大脳皮質一次運動野から、脊髄の運動ニューロンに直接投射している皮質脊髄路である(直接投射は霊長類のみの特徴)。われわれは一次運動野や皮質脊髄路に損傷を作成しても、適切なリハビリテーションを行えば麻痺が消失し、精密把握が段階的に回復することを見いだし、機能回復の行動解析を行うとともに、回復に関わる神経回路の構造変化、機能変化を電気生理学、組織学、分子生物学などの手法を用いて解析を行っている。背景の説明に加え、現在までに得られた知見を紹介する。
サル大脳皮質における動きと形の情報処理
三上章允(行動発現分野
目で見る世界では多くのものが動いています。見る対象だけでなく観察者も多くの場合動いています。このような環境で動くものの将来の位置を正確に予測することは、生存にとって重要な作業です。私たちが目標を目で追いかけるとき、目標が移動してもすぐに目は動かせません。脳が動きを検出し目を動かす指令を出し、目の筋肉が収縮するまでに時間がかかるからです。そこで、目が実際に動くまでに目標が動いてしまいます。普通は目標の動きから200ミリ秒(ミリ秒は1000分の1秒)程度遅れて、目が動きはじめます。目を動かすタイミングは毎回少しずつ違うのですが、脳は自分の目が動きはじめるまでに目標がどれだけ移動しているかを毎回正確に計算し正しい位置へ視線を移動することができます。この作業は無意識のうちにしかも短時間に行われます。さらに、目が目標に追いついた直後に目標の動きに合わせて目標を追いかけるように視線を移動させることができます。
動きの視覚はこのように生命にとって重要な役割を担い、無意識のうちに将来の位置を正確に予測する機能を備えています。動きの視覚は動きそのものの視覚としてだけでなく、奥行きの視覚や形の視覚にも重要な役割を演じています。例えば私たちが頭を動かすとき遠くのものはわずかにゆっくり動き近くのものは大きく速く動きます。運動視差とよばれる現象です。私たちが片目で奥行きを判断するときには、この運動視差が役立っています。また、動きの違いは形の識別にも重要です。動いている物体は静止した背景から容易に分離でき、物体の認識を容易にします。保護色の蝶は静止していると発見するのは困難ですが、動くとすぐに分かります。一面のランダムドットの中の一部の領域のドットを動かすと、その領域を形としてみることができます。静止した状態では全く図形は見えませんが、動きはじめると形が見えてきます。この現象はShape
From Motionと呼ばれます。
ところで、大脳皮質にはたくさんの視覚野があります。ヒトは、外界の視覚情報を眼球の後ろにある網膜上に2次元的に投影されます。大脳皮質の第1次視覚野と第2次視覚野には、網膜上に投影された位置、奥行き、動き、形、色、などの視覚情報のすべてがほぼ平等にもたらされます。第3次視覚野以降は、位置、奥行き、動きなどの空間情報は、第3次視覚野、3A野、第5次視覚野(MT野)などを経て、頭頂連合野へ送られます。一方、形や色などの形態情報は、VP野、第4次視覚野を経て、側頭連合野へ送られます。このように視覚情報の初期過程で、視覚情報処理は大きく二つの流れに分かれており、空間情報と形態情報は分離して扱われます。しかし、現実感のある視覚世界を脳内に再構成するためには、空間情報と形態情報は統合される必要があります。主として側頭葉に向かう腹側経路が関与する形態認知の場面では、色、明るさ、表面性状など形態視の要素ばかりでなく、動きや奥行きのような空間視の手がかりによっても形を識別することができます。また、ある物が動いているという認識には、形態と位置あるいは位置の移動の情報の統合が不可欠です。高次脳機能分科(行動発現分野)で取り組んでいるテーマの1つは、このように視覚情報の初期課程で分離されて処理される視覚情報がどのように統合されるかを明らかにすることです。
ニホンザルの進化遺伝学
川本 芳(集団遺伝分野)
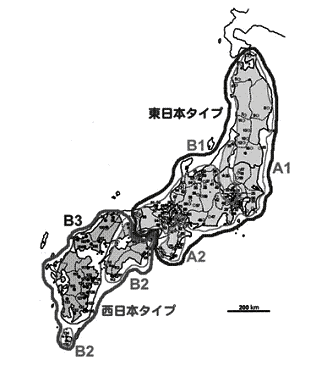 ニホンザルの祖先はいつごろ、どこから日本列島に入ってきたのでしょうか。また、入ったあとどのように定着したのでしょうか。こうした疑問に答える研究について紹介します。遺伝子のタイプをくらべて地域の関係を調べ、サルたちが日本列島に棲むようになった経緯を調べるには、どんなタイプの遺伝子がどこにどれくらいあるか、という情報が必要です。遺伝子のタイプが近いか遠いかという関係から遺伝子や生物の系統関係がわかります。また、どこにあるかという情報は、系統関係とはべつのことで、おたがいが地理的に近いか遠いかという空間の情報です。系統的に近いもの、つまり時間的に近い関係にあるものが空間的に近いところにあるとはかぎりません。祖先がきた道をさぐる方法として、遺伝子の系統関係と地理的な分布を結びつける考え方は重要です。
ニホンザルの祖先はいつごろ、どこから日本列島に入ってきたのでしょうか。また、入ったあとどのように定着したのでしょうか。こうした疑問に答える研究について紹介します。遺伝子のタイプをくらべて地域の関係を調べ、サルたちが日本列島に棲むようになった経緯を調べるには、どんなタイプの遺伝子がどこにどれくらいあるか、という情報が必要です。遺伝子のタイプが近いか遠いかという関係から遺伝子や生物の系統関係がわかります。また、どこにあるかという情報は、系統関係とはべつのことで、おたがいが地理的に近いか遠いかという空間の情報です。系統的に近いもの、つまり時間的に近い関係にあるものが空間的に近いところにあるとはかぎりません。祖先がきた道をさぐる方法として、遺伝子の系統関係と地理的な分布を結びつける考え方は重要です。
最近の研究ではミトコンドリア遺伝子という遺伝子がよく調べられています。この遺伝子は母から子供にしか伝わらない性質があります。分析がしやすく、短い時間でもタイプがかわりやすいなど、便利な性質があるので、たくさんの情報がとれます。
サルはもともと熱帯が原産で、雪深い日本の山に棲むようになったニホンザルは、世界中のサルでいちばん寒い場所に侵出した種類です。化石の研究によると、ニホンザルの祖先はおそくとも40-60万年前に大陸から朝鮮半島を経て日本列島に入り、本州に広がっていました。侵入した祖先は日本列島に安住できたわけではないようです。ミトコンドリア遺伝子の研究から、ニホンザルには大きく二つのグループがみつかり、東と西のサルが区別できました。岡山県と兵庫県あたりが境界になっています。遺伝子タイプの性質から考えて西のサルたちは古くから棲んでいるようですが、東では定着がおそかったように考えられます。おそらく、最後の氷期には、本州の山は寒冷化で棲みにくい森にかわり、祖先は西日本に追いやられたようです。氷期が終わり温暖な気候がもどってから、再び東北地方まで分布を拡げたと予想できます。
染色体・DNA分化と霊長類の進化
平井啓久・今井啓雄(遺伝子情報分野)
I:染色体の構造分化とその生物学的意義 平井啓久
染色体(ここでは真核生物に限定する)はDNA鎖がタンパク質によって束ねられてできた高次構造から成る巨大分子です。それゆえ染色体が構造的に変化すれば、その中に潜むDNAならびに遺伝子も影響を受けます。どのような影響を受けるかは、染色体変異の種類によって異なるでしょう。例えば、染色体構造変化の特性によって、多様性が高くなったり低くなったり、遺伝子の発現が偏向されたりすることが推測されます。
今回はインドネシアのテナガザルに最近起こった染色体変異(全腕転座)と種分化に関する解説、ならびにヒトとチンパンジーの表現型の相違を生む要因のひとつになると推測される染色体変異の紹介を行います。「ヒトらしさの形質」の進化の説明には、「タンパク質の進化」、「less-is-more」(遺伝子の減少がもたらす進化)、および「遺伝子の活性を制御するゲノム領域の変化」、の3つがあげられていますが、染色体の変化はそれらに総体的に関与するものと思われます。特に今回紹介する染色体末端の分化は、遺伝子沈黙や多様性の変化に関係していると思われ、ゲノムの進化に関わるホットスポットとして、最近注目を集めつつあります。
II:分子の性質を基盤とした霊長類の感覚研究 今井啓雄
ゲノム情報や分子生物学的方法が広まった現在、遺伝子情報とその産物であるタンパク質レベルの生化学的実験を基に、霊長類の感覚について、分子と生理反応や個体応答を結びつける研究が可能になってきました。例えばチンパンジーとヒトのゲノムを比べると、存在する遺伝子の種類は似通っていることがわかってきています。このことから考えると、それぞれの遺伝子産物がどのように発現し、どのような分子としての特性を示すのかということが、ポストゲノムの重要な課題ということになります。
私たちヒトは3種類の錐体光受容タンパク質を持つため、三原色(赤・緑・青)の色覚を示します。ところが、この三原色というのは動物一般から見るとかなり特異なケースであり、例えばニワトリは4種類の錐体光受容タンパク質を持ちます。また、マウスの錐体光受容タンパク質は二種類しかありませんが、ヒトにとっては紫外線と呼ばれる400
nm以下の光を受容することができます。このように遺伝子の種類や数が異なることは遺伝子を見ればわかりますが、生物の中ではそれぞれの分子の量や反応特性が違うため、生物の反応を分子の言葉で表すためには、これらのパラメータがどのように違うのか、どうしてそのようになるのか解明することが必要です。霊長類研究においても、視覚だけでなく様々な感覚について、こうした分子レベルのアプローチが重要になってくると考えられます。
最近の野外研究~ニホンザルを中心に
杉浦秀樹(社会構造分野)
霊長類の野外研究とは、どんなことをしているのでしょうか?私たちにもっとも身近な、ニホンザルを例に紹介します。
1)基本編 ~サルを見てみましょう
まずはサルを見ないと始まりません。調査地を決めてサルを探し、サルの頭数を数えたり顔を覚えたりします。これは同時にサルを観察者に慣らすことにもなります。全く調査をしていない状態から、サルを観察できるようにするのはなかなか大変です。最近では、すでに調査がされていて、条件の整った場所で行うことも多くなっています。
いくつかの調査地を紹介します。
2)中級編 ~サルを追いかけてみましょう
次はサルをじっくりと見たいものです。1頭のサルをずっと追いかけてその行動を見るという方法がよく使われます。単に「どんなことをしたか」という定性的な記録だけでなく、「どれくらいしたか」という定量的な記録をするのが普通になっています。
よく使われる記録方法を、簡単に紹介します。
3)応用編 ~サルを研究してみましょう
さまざまな工夫をして、研究を進めていきます。新しいテクニックを使うもよし、着眼点のユニークさで勝負するもよし、量で勝負するもよし、です。観察中に予期せぬ新現象を発見するかもしれません。
実際の研究の話をいくつか紹介します。
参考図書
・霊長類学を学ぶ人のために 西田 利貞, 上原 重男 (編集)
世界思想社 ISBN: 790707431
霊長類の野外研究を中心に幅広い話題が紹介されています。巻末の「読書案内」も充実しています。
・霊長類学生態学 霊長類生態学―環境と行動のダイナミズム
杉山幸丸(編著) 京都大学学術出版会.ISBN: 4876984069
霊長類の生態学研究を中心に、さまざまな研究が紹介されています。
・行動研究入門―動物行動の観察から解析まで
P. マーティン, P. ベイトソン (著), 粕谷英一, 細馬宏通,
近雅博(翻訳) 東海大学出版会.ISBN:4486011376
動物の行動をどのように観察するかについての教科書です。
・ニホンザルの自然社会―エコミュージアムとしての屋久島
高畑 由起夫, 山極 寿一 (編集) 京都大学学術出版会 .ISBN:
487698087X
屋久島で行われたニホンザルの野外研究が紹介されています。
チンパンジーの認知とその発達
友永雅己(思考言語分野)
チンパンジーは、現生霊長類の中で最もヒトに近縁であり、「進化の隣人」とも呼ばれることがある。彼らの行動や認知は私たちヒトにきわめて似た側面を持っていると同時に、非常に重要な相違も持っている。本講義では、比較認知発達という観点から、彼らの認知発達の過程と私たちヒトの発達過程を、社会的認知に関連するトピックを中心に比較していきたい。
チンパンジーの乳児にとって最も重要な社会的存在は母親である。これはヒトであろうがニホンザルであろうが変わりはない。チンパンジーの乳児は母親のおなかにしがみついてはいるが比較的高頻度で母子間の見つめあいを行う。ヒトではさらに音声による相互の働きかけが見られる。いずれにせよ、チンパンジーでもヒトでも「顔」の認識が初期の社会的認知の発達では重要な能力となる。チンパンジーの乳児では生後1か月程度で母親の顔を他のおとなの顔から区別できるようになる。さらに、2か月頃になると自分の方を向いた顔の方を視線がそれた顔よりもより長く注視するようになる。顔という刺激が乳児の注意を捕捉するのだ。このような現象はより成長した幼児やおとなのチンパンジーによる認知実験でも確認されている。そしてこの特性が母子間の見つめあいを促進し、発達初期の社会的関係の成立に寄与するのだろう。
顔に関連した興味深い社会的認知の現象として「共同注意」を挙げることができる。ヒトでは9か月から1歳頃になると、他者の視線の向いている方に自分の視線(=注意)を向けることができるようになる。このような能力を共同注意と呼ぶ。顔に向けられた注意を視線という手がかりによって「ひきはがし」て他者の注意の方向に向ける。このような能力自体はチンパンジーでも認められる。この共同注意はヒトでは自己と他者と外界の事象をつなぐコミュニケーションのツールとして非常に重要な役割を発達過程の中で担っていくようになるのだが、チンパンジーではそこまではいかないようである。他者の注意(を示すような行動)を単に自らの注意をシフトさせるための「手がかり」としてのみ利用しているかのようだ。さらに、幼児とおとなのチンパンジーを対象とした認知実験からは、ヒトとチンパンジーではこの社会的な手がかりによって空間的注意がシフトするメカニズムにも差異が存在する可能性が示唆されている。
共同注意を基盤とした社会的交渉の深まりは、その後の他者理解や「心の理論」の発達の出発点でもある。この出発点において存在するヒトとチンパンジーの間の「河」はおとなのチンパンジーの社会的知性の発現にも当然のことながら影響を及ぼしているものと思われる。
人間の知性の起源
正高信男(認知学習分野)
人間らしさとは何だろう。
凶悪な少年犯罪が、非常に頻繁に報ぜられるようになった。そのたびにマスコミは、「心の闇」という表現を用いる。けれどもこうした発想は、根本的に本質を見誤っていると私は思っている。
もっとも、一部の識者のように同様の事件が増加していないと言うつもりはない。なるほど彼らの指摘するように、数だけ見れば十代の犯行は第二次世界大戦後まもないころの方がはるかに多いだろう。また今日でも、中高年の犯罪件数が若年層を上回っているのは事実である。
だが問題は動機である。
金銭に困って罪を犯すのと、そうでないものを区別しない議論は、まったく意味がない。詳細が明らかになったのちも「どうして、こんなことを……」と行動の理解に苦しむ事件は、間違いなく増えていると思う。その上で、あえて私は、「心の闇」というレッテルを貼ることが見当はずれだと考えている。
私たちが自分自身の行いを説明できるのは程度の差こそあれ、心のなかでことばによる判断を下しているからにほかならない。人間は外界へ向けて表明することなくとも、言語情報を操作することができる。心理学者はこれを内的言語と呼ぶ。およそ思考というものの基礎とされてきた。
しかしながら、このような意思決定の方法はヒトがなし得るそれのすべてではない。それどころか、長い間の養育と教育を経てようやくたどりつく一つの到着点にすぎない。心のなかで視覚的イメージが次々とフラッシュするだけで行為にいたるような過程が存在しても、全然おかしくない。そこにはおよそ闇など存在しない。
今からおよそ60年前、アルベール・カミュはすでにこれに気づいていた。今ではほとんど省みられなくなった作品『異邦人』の主人公ムルソーは、母の死の翌日、海水浴に行き、女と関係を持ち、映画を見ては笑いころげ、あげくのはてに友人の女出入りに関係して人を殺し、動機を「太陽のせい」と答える。判事に自分の行動を要約して、「レエモン、浜、海水浴、争い、また浜辺、小さな泉、太陽、そして、ピストルを5発撃ちこんだこと」(窪田啓作訳、新潮文庫、72ページ)と答えるだけである。正岡子規の表現を借りるならば、私たちは「一匹の人間」として生を授かるのだ。
そして21世紀に突入した日本において、成人してなお「一匹」として暮らすものの数は、急増しつつある。ヒトの行動の生物学的基盤を研究するものにとって、ありのままの「一匹」の姿を身近に観察できるのは、ある意味で幸甚の限りであるが、どうしてこんな事態にいたったかをを話す予定である。
マカクザルの身体形態に見られる多様性の謎を探る
濱田 穣(形態進化分野)
マカクザルはアジアに広く分布しているサルです。分類的には、霊長類からはじまり、真猿類・狭鼻猿類・オナガザル類に属します。ニホンザルもその1種です。オナガザル類はその近縁の類人猿・人類グループとは3000-2500万年前に分岐し、独自の適応放散を遂げ、現在のような分布や多様性を獲得しています。マカクはアフリカ西北端に分布する一種を除き、他はすべてアジアに生息していますが、アフリカでヒヒやマンガベイのグループから分岐(起源)したと推定されています。化石マカク類から推定される進化過程は、高井先生の講義で詳しく解説されますが、現在19-21種に分類されるほどに多数の種を含むこのグループの進化過程は、とても複雑です。しかし、私たちマカク調査グループは、さまざまな専門から、その進化史再構築に挑戦しています。
私たちが今、ターゲットにしているのは、アカゲザルとカニクイザルです。この二種は近縁であり、また、ニホンザルやタイワンザルと同じ種群を形成すると考えられています。この二種はそれぞれがひじょうに広い地理的分布をもち、しかもインドシナ半島部で、その分布境界が接しています。そこには、分散の自然障壁は存在しないため、生態学的競合によって、南北に分布域を分けていると考えられます。しかし、その境界域に生息している個体群では、多かれ少なかれ、交雑(異種間遺伝子浸透)が推測される、形態学的特徴が見られ、また、少数のサンプルに基づく遺伝子系統解析結果でもそれが支持されています。このような交雑があることは、「生物学的種概念」を厳密に適用すれば、この二種は未確立では、との疑問も生じます。
現生マカクに関する研究の現状では、地域個体群の変異性の実態に関するデータがほとんどありません。二種の境界周辺地域において、フィールド調査をいま、インテンシブに行なう必要があります。マカク個体群とその生息地の保全にむけて、さかんに活動されていますが、地域個体群の絶滅は、確実・急速に進んでいるからです。わたしたちは、タイ・ベトナム・ラオス・ミャンマー・バングラデシュと二種の境界域が推定されている5カ国で、分布・生息実態調査(アンケート調査と巡回調査)、および一時捕獲あるいは非接触サンプリング(写真計測法、糞など)によって調査をすすめています。この講義では、明らかにされたマカク進化史の一端を紹介します。
ユーラシアの東と西:マカクの進化史
高井正成(系統発生分野)
マカク類(Macaca属)の起源は、現在判明している化石記録から後期中新世(約700-600年前)の北アフリカと考えられている。その後、中新世末期にアフリカ大陸から中東地域を経由してユーラシアに進出し、ヨーロッパからアジアにかけて分布域を広げていった。ヨーロッパに進出したマカク類は気候変動に伴いほとんどが絶滅してしまい、現在はアフリカ大陸北西端と対岸のイベリア半島南西端に依存種(バーバリーマカク)として残っているだけである。
一方、アジア大陸を東進したグループは、南?東アジアにかけた広い地域に生息するようになり、現在のような生息パターンを示すに至った。現在東南アジアに生息しているマカク類は鮮新世以降の約500万年の間に分化を遂げたと考えられている。つまり北アフリカ北西部のバーバリーマカクとアジア東部のマカク類は、約600万年前の共通祖先から分岐してユーラシア大陸の東と西で独立して進化してきたのである。したがってバーバリーマカクの変異とアジア産マカクの変異は、約600万年におよぶ環境変動とそれに伴う隔離現象がそれぞれの系統内での進化にどのように影響を与えたかを示している。
ヨーロッパで見つかる鮮新世?更新世前半の化石マカク類は、現在全てバーバリーマカクの亜種または近縁種としてまとめられている。これに対し、東南アジアのマカクは複数の種群に別れ約20種に分類されている。マカク類の進化にみられるこのような種分化レベルの「非対称性」の原因としては、おそらくヨーロッパが(アルプス山脈のような山地の障害があるものの)全体的に連続した陸地であり、寒冷化などの気候変動があったとしても完全な地理的隔離現象が起こりにくかったのに対し、東南アジアでは海水面の変動により島嶼化と連結を繰り返した地域が多く、集団の隔離や融合が起こりやすかったため、マカク類の種分化が急速に生じたと考えられる。
またアジア産マカクの系統と分布域の変遷に関しては、南?東南アジア地域を中心とした古分布域の変遷が推定されてきた。しかし近年中国北部の山西省楡社で見つかった中新世末のマカク類の遊離歯化石(上顎大臼歯)はかなり大型で、その地点もかなり高緯度である。南アジアのシワリク地域でみつかっているM.
palaeindicaやsinica groupの歯よりも一回り大きく、分布域もかなり離れている。従来の仮説に従えば、比較的小型のマカクがアフリカ大陸からユーラシアに侵入し、南アジアを経由して東アジアに達して、さらにそこから北方に進出する過程で大型化したことになるが、ユーラシア大陸への侵入時期がさらに早まることになり、北アフリカ及びヨーロッパの化石記録との整合性が無くなってくる。これまで提案されてきたアジアのマカク類の進化プロセス仮説の見直しを含めて、地球規模の環境変動の中でどのようにマカク類が進化してきたか、巨視的な観点からみた最新の研究状況を紹介する。
霊長類の生殖器構造から見えてくるもの
松林清明(人類進化モデル研究センター)
生殖器は種の存続にとって極めて重要な生殖活動を司る器官であり、その構造は進化を考えるときに大きな手がかりを与えてくれる。
大型類人猿を例にとり、先ず雄性交尾器としてのPenis
のサイズを見てみる。大きな体格とは不釣合いに小さくて目立たないゴリラ、オランウータン。それと対照的に、チンパンジーは長さが目立ち、ヒトはさらに長さ・太さともに際立って大きなサイズを持っている。これは当然ながら雌性交尾器の構造と密接に関連しているが、種としてどんな背景を持っているのか。またそれぞれの種の進化とどのように関わるのか。
配偶子産生にあずかる精巣の構造も、各種に特有な特製を示す。チンパンジーは体格比でも精巣自体のサイズでも、他種よりはるかに巨大である。ゴリラ・オランウータンは精巣も極めて小さく、ヒトは中間ぐらいである。
精巣はその主機能を考えると、全体の形態は余り意味を持たないので、組織学的な検討が必要になる。内景として重要なのは、造精器官としての精細管と内分泌器官としての間質である。各大型類人猿はどのような特徴を持つのか、そしてその意義は何かを考える。
精液に含まれる精子の数の検討も重要となる。
カギになるのは各類人猿種の繁殖様式である。繁殖単位の基本構成としては、単雄群~複雄群~弧在型に分かれるが、それが生殖器構造にどう影響したのだろうか。
動物園で飼育中に死亡したゴリラの精巣組織像は、精細管がガラス様変性を起こしている例が多いことも特筆される。この種が持つ生殖器系の脆弱性は、何を示すのだろうか。
体格サイズ自体や体格の性的2型も繁殖様式と密接に関連していると考えられる。ハーレムタイプの繁殖単位を持つサル種からペアタイプの種までを見通すと、体格の性差と繁殖単位の関係に一定の傾向が認められる。単雄群を作るゴリラはオスの絶対サイズが大きく、またメスとの性差も大きいのに対し、チンパンジーはそのいずれもゴリラより小さい。
これが繁殖戦略とどう結びつき、生殖器構造にどう反映されているのか。
これらの各要素を照らし合わせると、ヒトが本来備えていた繁殖様式が大型類人猿各種の間のどのあたりに位置するのかが推測できる。これはまた、ヒトのたどった道筋を考えるうえで、社会学的・経済学的な諸課題をも提示する。 ヒトの身体に見られる特殊化の象徴として、脳や手足・喉頭などがよく語られるが、化石にも残らず、見落としがちな生殖器に光を当てて進化のひとつの姿を捉える。







